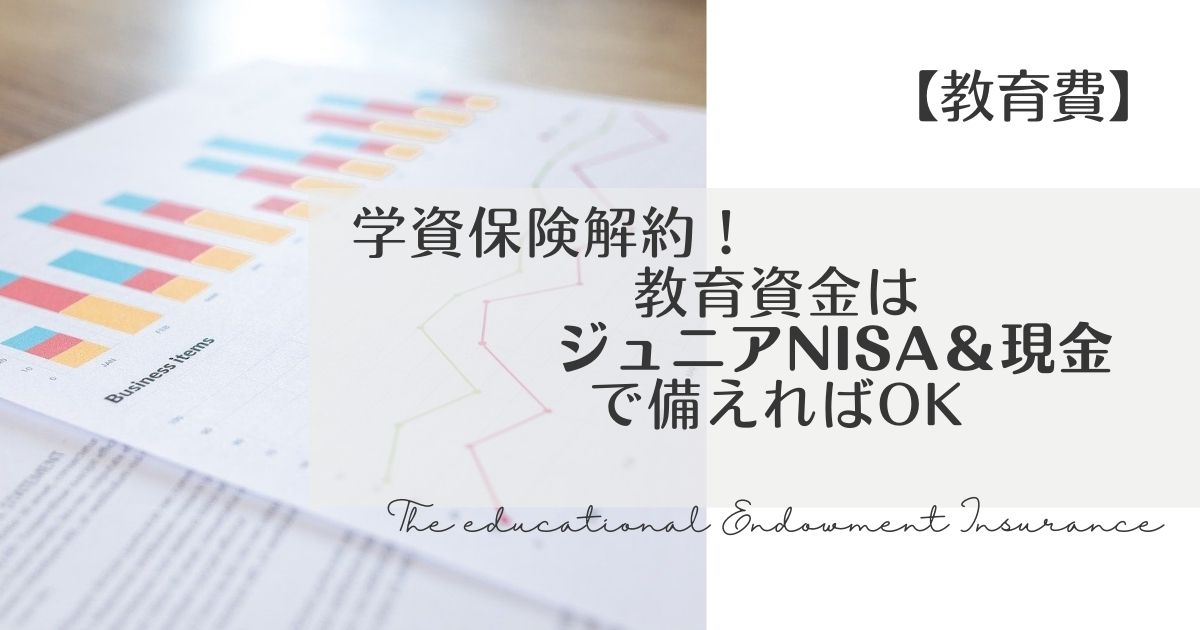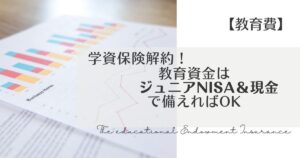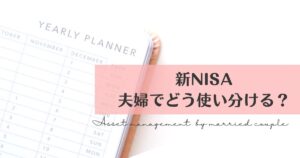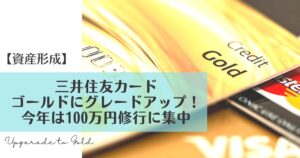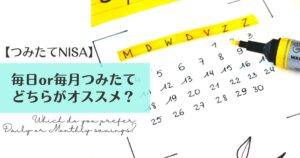こんにちは!
3姉妹を育てる事務員かあさんちばっちです。
自己紹介はこちら
さて。
うちには小4、小2、年中の3姉妹がいます。
私は3人目をどうするか考えた時
「教育費たりないかも・・・」
「子供の教育費にはいったいいくらかかるんだろう・・・」
ととても不安になったことがあります。
でも結局
「やっぱり3人ほしい!お金はなんとかなるさ!」
と勢い任せにしちゃいました(笑)。
でも現実問題としてやっぱり子供にはお金がかかります。
そして一番の心配は“大学の学費”ですよね。
私は長女が生まれてすぐにとりあえずのつもりで学資保険に入り、
その後次女、三女も特になにも考えずに入れました。
「現金貯金よりちょっとは増えるはず」
たしかにその可能性はありますが、
投資を勉強し始めたら学資保険に入ってるメリットがほとんどない、
ということがわかったので、つい最近解約し、
教育費はジュニアNISAと現金で備えるという方針に決めました。
- 2023年まではジュニアNISAに全力投資
- その後は月10,000円を現金貯蓄
学資保険解約の返戻金 公開
学資保険と同時に私が加入していた医療保険も解約しました。
この医療保険の解約では50万円以上減って返ってきました(涙)。
減ってしまったのは悔しいけれど、戻ってきた分をインデックス投資で長期運用に回せば全く問題ありません。
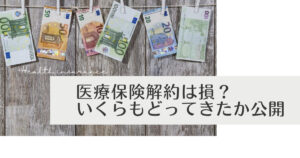
では学資保険はどうだったのでしょうか?
【長女】
・払込期間9年7ヶ月
・既払込保険料1,152,576円 →返戻金 1,152,576円
・差額 0円
【次女】
・払込期間7年8ヶ月
・既払込保険料946,368円 →返戻金941,472円
・差額 ▲4,896円
【三女】
・払込期間4年3ヶ月
・既払込保険料592,416円 →返戻金540,336円
・差額 ▲52,080円
加入したときの条件とか、払込期間によって大きな差がありますね。
三女の52000円〜 どこいっちゃったの〜(涙)
と叫びたい気持ちになりますが、気にしなくていいんです!
戻ってきた分をジュニアNISAで運用すればちゃんと取り戻せますから!
なんで学資保険を解約したの?
なぜ学資保険を解約したかというと
投資と同じく学資保険にも絶対はなく、
大きなメリットもなく、
それどころかいろんなリスクがある、ということを知ったから。
《学資保険のデメリット》
- 利回りがめちゃくちゃ悪い
- 18年間資金拘束される
- 満期時の元本割れのリスクもある
つみたてNISAで少し投資というものをやってみると、
学資保険に月々払う金額を自分で選んだ投資信託で投資運用したほうがムダがないしちゃんと増やせる、
と確信したので解約して自分で投資運用しようと決めました。
ジュニアNISAで運用中
未成年口座開設は正直めんどくさい
2019年から3人ともジュニアNISAをやっています。
私が投資に興味を持ち始めたのが2018年。
まわりに「つみたてNISAやってるよ!」なんて人が一人もいなくてヒーヒー調べながらつみたてNISAを始めたものの一時息切れ。
ジュニアNISAが2023年に廃止されることがわかっていて、
「5年の投資可能期間をなんとか確保せねば!」
ということで翌年2019年に子供3人の楽天銀行と楽天証券を開設してジュニアNISAをはじめました。
ただですねー、未成年の口座開設って
・・・ホントめんどくさい!!
親の身分証明書のコピーだとか、住民票だとかすべて郵送。ぐはっ
そのあとネットで楽天銀行と楽天証券それぞれのIDとPWを設定。
口座開設にそれぞれメアドが必要となったけど子供はメアドなんかもっていないのでoutlookを登録し・・・
すべて×3人分。しんど。ID&PW管理地獄ダヨ♪
自分のつみたてNISAを始めるだけでもヒーヒー言っていたのに3人分。
正直始める前がめちゃくちゃ大変でした。
投資資金はどうしたの?
ジュニアNISAの投資資金はどうしたかというと
- お祝い金
- 児童手当
- 月々のつみたて&ボーナス
これらを投資に回しています。
それぞれの口座で管理
子どもが生まれたときにそれぞれの銀行口座を作り(このときは三菱UFJ)、
出産祝や七五三、入学祝、お年玉など、いただいたお金は1000円でもきっちりそれぞれの口座に分けて入れていました。
また、児童手当も同じようにそれぞれの口座に分けるようにしてきました。
あとは私が月々5000円ほど、余裕があるときにはボーナスから数万ずつ入れたりしてきました。
※当時はこれとは別に学資保険にそれぞれ1万ほどいれてました
たかが月々5,000円でも3人分となると一年で18万円。
突然出せといわれてもなかなかだせません。コツコツちりつも。大事です。
ジュニアNISA開始時にはまとまった資金に
お祝い金や児童手当など、頂いたお金だけでもこうして口座をわけて入れておいただけでまとまった資金になっていました。
長女の場合はジュニアNISAを始める時点で一年の上限80万円の3年分近くが口座にたまっていたので、
投資資金についてそこまで考えなくても大丈夫でした。
一方で三女は2018年生まれなのであまりまとまった資金がありませんでした。
「どうしよう・・・何十万も出せない・・・」
と悩んだのですが、
「運用期間が長くなるから時間を味方にすればいいや〜」
と考えることにして、
「上限の満額絶対入れなきゃ!」とあまり追い詰めないようにしました。
だって80万円×3人=240万/年とかムリ(笑)
もちろん満額入れたほうが利益も大きくなりますし、税金の面でも得です。
でもなにがなんでも80万!とかいってもないものはないので(笑)、
とにかく児童手当と月々コツコツ、少しでも回せれば回す、というスタンスでやっています。
ジュニアNISA終了後は現金で
ジュニアNISAでインデックス投資運用していれば増える可能性はとても高いです。
現時点でもしっかりプラスの含み益になっています。
私のつみたてNISAよりよっぽど増えててうらやましいくらい(笑)つみたてNISAの上限が40万円だからしかたないけど。
とはいえ投資には絶対がありません。減る可能性ももちろんあります。
ということで、教育費を投資の運用だけで用意するのはリスクがあるので
ジュニアNISA終了の2023年以降はガッチリ現金貯蓄するのがベターかと思います。
現金でいくら貯蓄できるかシミュレーション
小4長女の場合(2022年時点)、ジュニアNISA投資期間終了後(2023年度以降)から大学入学までにどのくらい現金で貯蓄できるかざっと計算してみました。
※大学の学費に一番お金がかかるため大学費用でシミュレーションしているだけで、絶対に大学進学しなきゃいけないとしているわけではありません。
①月10,000円ずつ貯金
2024年 小6〜2030年高3 →7年
10,000円×12ヶ月×7年=840,000円
②児童手当
2024年小6〜2027年中3 →4年
10,000円×12ヶ月×4年=480,000円
①+②=1,320,000円
もちろん児童手当制度もいつ廃止されるかわかりませんし、
条件が変わって所得制限で貰えない、ということも考えられます。
「児童手当がなくなったらどうしよう・・・」
と心配ならボーナス時に6万入れるというのも一つの手段です。
とりあえず月々10,000円ずつコツコツ現金で貯めるだけでも
84万円は確実に貯められます。
いずれにしろリスクあり・メリットなしの学資保険に掛けていた10,000円をそのまま現金貯蓄にするだけなので
私の銀行口座の自動振込設定で3人それぞれの口座に毎月送金してしまえばOKというわけです。
つかいやすくなったジュニアNISA
18歳までの払い出し制限がなくなった
これまでジュニアNISAは利用者が増えず、2023年度に廃止されることになりました。
ところが廃止は決定されてますが制度の内容が改正されたため、
2024年以降、
“18歳までの払出し制限がなくなり、いつでも自由に払い出し可能” となり、
とっても使いやすくなりました。
よくよく考えてみると学資保険もこの18歳まで自由にお金の出し入れができないという資金拘束がデメリットの一つなんですよね。
自分のお金なんだから自由に使いたいときに使わせてくれよってかんじですね。
でも実は私は“払い出し制限”がそんなに使いづらいものだとかは知らずにジュニアNISAをはじめました。
「とにかく早くはじめなきゃ−!!」
みたいな状態で、そんなこと気にしている余裕なかったんです。笑
でもこの払い出し制限があるせいで
私立の高校に行くことになって18歳より前にまとまった資金が必要になった! とか、
大学入学直前に株が暴落! とか、
まあまああり得そうなことに全く対応できないんですよね。それで人気がなかったと。
なんだか皮肉な話ですが、廃止が決まってから加入者が急増しているとか・・・
ということで私はたまたまではありますが、
「あぁ、あの時3人分の口座開設がめんどくさすぎてノイローゼになりそうだったけど(大げさ)、始めといてよかったー!!」
と思っています。
今からでもジュニアNISA始めたほうがいい?
2023年で制度が撤廃となると、今からジュニアNISAを始めてももう遅いと思ってしまう方もいると思います。
あくまで個人的な意見ですが、私は始めた方がいいのではないかと思っています。
来年とはいえあと2年分、80万円×2年=160万円 は投資可能です。
子供が小さければ小さいほど運用期間が長くなりますから、今から始めて160万円ほったらかし運用しておくだけで
銀行に預けているより増える可能性が十分にあります。
ピンと来なければネットの運用シミュレーションサイトなどで計算してみるとよくわかります。
でもこれだけは注意してください。投資には絶対がなく、すべて自己責任です。
そのことをよく考えた上で教育費をどうするか決めていけばいいと思います。
教育費はジュニアNISAと現金貯蓄で備えよう
ジュニアNISAも学資保険も絶対がなく、リスクがあります。
でも現金だけではまったく増えないので教育費のすべてを現金で用意するのは大変。さらにインフレに対応できません。
ということで、メリットのない学資保険はやめて
- 2023年まではジュニアNISAに全力投資
- その後は月10,000円を現金貯蓄
という2本立てやり方で教育費を用意することにしました。
ジュニアNISAを始めるか悩んでいたり、教育費をどう貯めようか悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。
以上ちばっちでした!